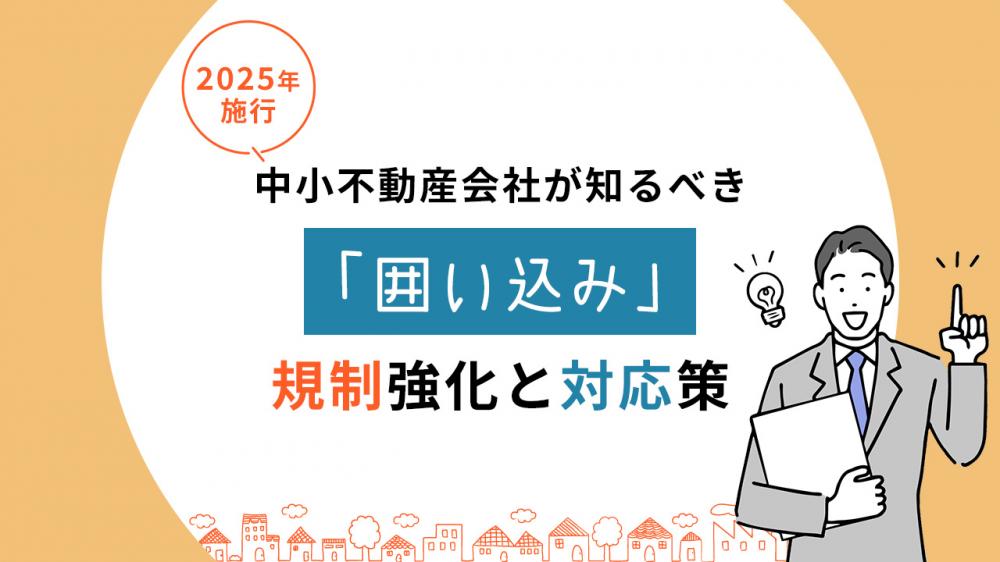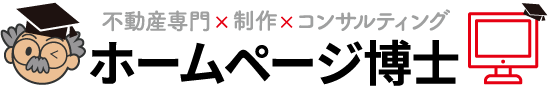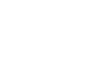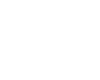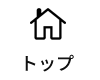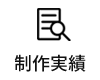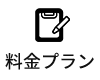2025年1月、不動産業界における「囲い込み」行為に対する規制が強化され、透明性の向上が図られました。この改正は、売主と買主双方の利益を守ることを目的としており、不動産取引の公正性を高めるものです。
特に中小不動産会社にとっては、これらの変化に迅速かつ適切に対応することが求められています。今回の記事では、「囲い込み」の背景と問題点、規制強化と対応策について解説します。
「囲い込み」とは何か?その背景と問題点

不動産業界における「囲い込み」は、取引の透明性や公正性を損なう行為として問題視されています。
この章では、囲い込みとは何か、そしてその背景と問題点について、次に挙げる4つの視点から見ていきましょう。
・囲い込みの定義と手法
・囲い込みが引き起こす問題点
・過去の事例と業界の反応
・2025年1月施行の規制強化の内容
囲い込みの定義と手法
囲い込みとは、売主から物件の売却を依頼された不動産仲介会社が、物件情報を他社に開示せず、自社の顧客だけで取引を成立させようとする行為です。この手法により、仲介会社は両手取引(売主買主双方からの手数料取得)を狙います。
具体的には、物件情報を公開せず、自社内でのみ情報を流通させることで、他社の介入を防ぐ手法で、売主にとって最適な買主とのマッチング機会を減少させる可能性があります。
また、市場全体の情報流通を阻害し、適正な価格形成を妨げる要因ともなりかねません。さらに、買主にとっても選択肢が制限されるため、公正な取引環境が損なわれることになります。
結果として、業界全体の信頼性が低下し、不動産市場の健全な発展を阻害する要因となるでしょう。このような背景から、囲い込みは問題視されています。
囲い込みが引き起こす問題点
囲い込みは、売主の売却機会の損失を招く可能性があります。物件情報が広く共有されないため、より良い条件の買主と出会う機会が減少するからです。
また、価格競争の抑制も問題です。情報が限定されることで、競争入札が行われず、結果的に市場価格より低い価格での取引が行われる可能性があります。
さらに、取引の不透明化も指摘されています。情報が公開されないことで、取引の公正性や透明性が損なわれ、消費者の信頼を失うリスクがあります。
過去の事例と業界の反応
過去には、囲い込みによるトラブルが報告されています。例えば、売主が知らない間に低価格で取引が成立していたケースなどです。
これらの事例を受けて、業界内では囲い込みに対する批判が高まりました。不動産業者間での情報共有の重要性や、透明性の確保が強調されるようになったのです。
また、業界団体や行政も、囲い込み防止のためのガイドライン策定や監視体制の強化を進め、市場の健全化と消費者保護が図られています。
【おすすめ記事】
不動産会社向けCRM(顧客管理システム)選びのポイントとおすすめに関しては、以下の記事でくわしく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
不動産会社向け!CRM(顧客管理システム)選びのポイントとおすすめ5選
2025年1月施行の規制強化の内容
2025年1月、不動産取引の透明性と公正性を高めるため、宅地建物取引業法施行規則が改正されました。この改正により、物件情報の登録義務の厳格化、取引状況の透明性向上策、そして違反時の罰則内容が強化されています。
物件情報の登録義務の厳格化
改正により、専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結した不動産業者は、指定流通機構(レインズ)への物件情報登録が義務付けられています。物件情報の迅速かつ正確な登録が求められるようになりました。
さらに、物件の取引状況を「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」などのステータスで最新の状態に更新することが求められています。他の仲介業者や消費者が、正確な情報を得られる環境が整備されました。
これらの措置は、物件情報の透明性を高め、不動産取引の公正性を確保することを目的としています。また、業者間の健全な競争を促進し、消費者の信頼性向上にも寄与するでしょう。
取引状況の透明性向上策
売主が物件の取引状況をリアルタイムで確認できる「登録証明書」の交付が義務化されました。この証明書にはQRコードが追加され、売主はスマホなどで簡単に専用画面へアクセスし、物件の状況を確認できる仕組みが導入されています。
売主は自らの物件の取引状況を把握しやすくなり、取引の透明性が向上しました。また、売主が取引状況をリアルタイムで確認できることで、不動産業者への信頼性も高まっています。
さらに、取引の透明性向上により、売主と買主の双方が安心して取引を進められる環境が整備されました。これらの施策は、不動産取引の透明性と公正性を高めることを目的としています。
違反時の罰則内容
2025年1月以降、囲い込みが確認された宅建業者は指示処分や業務停止処分の対象となります。例えば、レインズにおける物件の取引状況と実際の状況が異なる場合、不動産会社に行政指導が入る仕組みが整備されました。
これらの罰則強化により、不動産業者は法令遵守の重要性を再認識して適切に運営するよう求められています。また、違反行為が発覚した場合の社会的信用の失墜も懸念されるため、業者間での自律的な監視体制の強化も期待されています。
これらの規制強化の目的は、不動産取引の透明性と公正性を高め、消費者保護を強化することです。また、業界全体の信頼性向上にも寄与することが期待されています。
【おすすめ記事】
今、業界で注目されている「不動産コンバーター」の導入による業務効率化に関しては、以下の記事でくわしく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
不動産コンバーターの導入で業務効率化!不動産会社が知っておくべきポイントとは?
中小不動産会社が取るべき対応策

2025年1月の規制強化により、不動産取引の透明性と公正性が強く求められるようになりました。中小不動産会社は、これに適応するための具体的な対応策を講じることが重要です。
この章では中小不動産会社が取るべき対応策として、次に挙げる3項目を解説します。
1. 社内コンプライアンス体制の強化
2. レインズへの適切な情報登録と管理
3. 透明性を高めるための顧客対応
社内コンプライアンス体制の強化
法令遵守のための社内教育や監査体制の整備が必要です。従業員への定期的な研修を実施し、最新の法改正や業界の動向を共有することで、法令違反のリスクを低減できます。
また、内部監査の仕組みを導入し、業務プロセスのチェックを行うことで、コンプライアンス体制を強化できます。さらに、倫理規範や行動指針を明確に定め、全社員に周知徹底することが重要です。
組織全体での法令遵守意識を高め、不正行為の抑止につながります。外部の専門家を招いたセミナーや講習会の開催も効果的な手段と言えるでしょう。
加えて、匿名での内部通報制度を設けることで、従業員が不正を報告しやすい環境を整備する姿勢が求められます。早期に問題を発見し、適切な対応を取ることが可能となります。これらの取り組みは、企業の信頼性向上にも貢献するでしょう。
レインズへの適切な情報登録と管理
物件情報の正確かつ迅速な登録と、ステータスの適切な更新が求められます。
レインズへ(指定流通機構)の登録は、物件の公開状況を「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」など、最新の状態に保つことが重要です。他の仲介業者や消費者が正確な情報を得られ、取引の透明性が確保されます。
また、登録内容の定期的な見直しを行い、情報の正確性を維持することが必要です。誤った情報や古い情報が残っていると、取引の遅延やトラブルの原因となるおそれがあります。
専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結した場合、レインズへの物件情報登録が義務付けられており、その内容の迅速性や精度が求められます。
さらに、担当者間での情報共有を徹底し、物件情報の更新漏れや誤りを防ぐ体制を構築することが重要です。社内の業務効率化と、顧客満足度の向上が期待できます。
透明性を高めるための顧客対応
取引状況の適切な説明や情報提供を行い、顧客からの信頼を築くことが重要です。
売主には、物件の取引状況をリアルタイムで確認できる「登録証明書」を交付し、透明性を確保します。顧客は自身の物件の状況を随時把握でき、安心感を持って取引を進めることができます。
また、定期的な進捗報告や、問い合わせへの迅速な対応を心掛けることで、顧客満足度を高めることが可能です。取引に関する疑問や不安を解消するためのFAQの作成や、専用の相談窓口を設けることも有効でしょう。
これらの取り組みは、顧客との信頼関係を強化し、リピーターの獲得や口コミによる新規顧客の増加につながります。
さらに、取引の透明性を高めるために、物件情報や契約内容をわかりやすく説明する資料やガイドラインを提供することも効果的です。
【おすすめ記事】
中小不動産会社が知っておくべきCSR活動のポイントについて、以下の記事で特集しています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
中小不動産会社が知っておくべきCSR活動のポイントとは?
規制強化がもたらすメリットとデメリット

2025年1月から施行された不動産取引における「囲い込み」規制強化は、業界全体にさまざまな影響を及ぼしています。これらの変化は、売主買主、不動産会社それぞれにメリットとデメリットをもたらしました。
売主買主へのメリット
規制強化により、物件情報の透明性が向上し、売主はより多くの買主候補と接触できるようになりました。適正価格での売却が期待でき、売主の利益が守られます。
一方、買主にとっても物件情報へのアクセスが容易になり、選択肢が広がりました。希望する条件に合った物件を見つけやすくなり、満足度の高い取引が可能となります。
さらに、取引の透明性が高まったことで、売主と買主の双方が安心して契約を進められる環境が整備されました。不動産取引全体の信頼性が向上しています。
不動産会社へのメリット
規制強化により、不動産業界全体の透明性と公正性が向上しています。業界全体の信頼性が高まり、健全な競争環境が整備されました。
また、透明性の向上は、優良なサービスを提供する不動産会社にとって差別化の機会となります。顧客からの信頼を獲得し、ビジネスの拡大につなげることが可能です。
さらに、業界全体のイメージアップにより、新たな人材の参入や投資の促進が図れます。
考えられるデメリットとその対策
一方で、規制対応のためのコスト増加が不動産会社にとってのデメリットとして挙げられます。新たなシステム導入や社員教育など、初期投資が必要となる場合があります。
また、規制を回避しようとする不正行為のリスクも否めません。これに対しては、監督機関による厳格な監視と適切な罰則の適用が必要です。
さらに、過度な規制により業務が煩雑化し、効率が低下する可能性もあります。これを防ぐためには、業務プロセスの見直しや効率化を図ることが重要です。
【おすすめ記事】
不動産業界の人材不足を解決するための、中小不動産会社の採用とリテンション戦略ついて、以下の記事で特集しています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
不動産業界の人材不足を解決!中小不動産会社の採用とリテンション戦略
今後の不動産業界の展望と中小企業の戦略

不動産業界は技術革新や市場の変化により、新たな局面を迎えています。中小企業が持続的な成長を遂げるためにはこれらの変化に適応した上で、次に挙げるような3つの戦略が必要です。
1. テクノロジーの活用による業務効率化
2. 顧客ニーズに応えるサービスの提供
3. 業界団体との連携と情報共有
テクノロジーの活用による業務効率化
近年、AIやRPA(ロボティックプロセスオートメーション)の導入が不動産業界で進んでいます。これらの技術は、物件情報の管理や契約書類の作成など、従来手作業で行っていた業務を自動化し、効率化を図ることが可能です。
また、オンライン内見や電子契約の普及により、顧客対応の迅速化と利便性の向上が期待されています。さらに、データ分析を活用した市場動向の把握や、AIによる価格査定の精度向上も進んでいます。
顧客ニーズに応えるサービスの提供
顧客の多様化するニーズに対応するため、不動産業界では新たなサービスの提供が求められています。例えば、オンラインでの物件探しや、バーチャル内見といったデジタルサービスの充実が挙げられます。
また、チャットボットを活用した24時間対応のカスタマーサポートや、AIによる最適な物件提案など、顧客満足度を高める取り組みが進行中です。これらのサービスは、顧客との信頼関係を築き、競争力を維持するために重要です。
さらに、スマートホームやIoT技術を活用した付加価値の提供も注目されています。3
業界団体との連携と情報共有
中小不動産会社が最新の法令や業界動向を把握し、適切な対応を行うためには、業界団体との連携が不可欠です。業界団体は、法令や規制に関する情報提供や、研修セミナーの開催を通じて、企業のコンプライアンス強化を支援しています。
また、会員同士の情報交換やネットワーク構築を促進し、新たなビジネスチャンスを創出する場を提供しています。これらの連携を通じて、中小企業は業界全体のベストプラクティスや最新情報にアクセスし、変化する市場環境に柔軟に対応できるようになります。
さらに、共同での研修や情報共有により、業界全体のレベルアップが期待されます。
まとめ

2025年1月に施行された「囲い込み」規制強化は、不動産取引の透明性と公正性を高める重要な一歩となりました。売主と買主の双方が適正な情報を得られる環境が整備され、業界全体の信頼性向上が期待されています。
中小不動産会社にとって、これらの規制に適切に対応することは、法令遵守のみならず、顧客からの信頼を築く上でも不可欠です。社内のコンプライアンス体制の強化や、物件情報の適切な管理、そして顧客への丁寧な情報提供が求められます。
今後の不動産業界では、テクノロジーの活用や顧客ニーズに応えるサービスの提供が競争力の鍵となるでしょう。業界団体との連携や情報共有を通じて、変化する市場環境に柔軟に対応し、持続的な成長を目指すことが重要です。